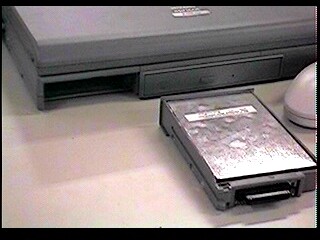
ここまで来たら、810MBのHDDも何とかしたい。
Apricotは、HDDも簡単に(工具なしで)抜くことができる。
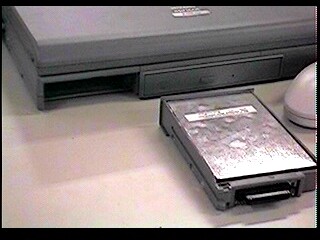
データを自分のところに置いて、APをそこそこ入れたらすぐ満杯になってしまうし、DriveSpaceを使うには、マシンパワーがしょぼ過ぎるし...
金をかけずにやりたいので、2.5InのHDDを物色していたら、TwoTopで2GBで19,800円の9.5mm富士通製ドライブを発見。
元に入っていたのはIBMの17mm厚だったが、値段に負けたうえに「ネジ位置は変わらんじゃろ」という安易な読みで買ってしまった。
家に帰ると、やはりネジ穴が合わない。
IBMは、真ん中辺にあるのだが、最近の2.5Inははじの方にネジがある。

上の写真が元のHDD(IBM製)。両はじから1/3ぐらいのところにネジ穴がある。


仕方がないので、ドリルでHDDケース(外枠)の方に穴を空けた。
本来は4カ所で止めるのだが、面倒だった事と2カ所で十分止まったので、そこで辞めてしまった。
また、内側のブリキのケースは、穴を開けるにはペラペラなので、ニッパーとペンチで「引きちぎって」穴を開けてしまった。


物理的には1時間もかからなかったのだが、この後、使えるまでが長かった・・・
ApricotのBIOSはPhoenixなのだが、これに大分「してやられた」のである。
(他のノートで、PhoenixのBIOSの物は同じ様な目に遭っている人が結構いるようだ)
詳細は、後日のUpdateで・・・
[1998.12.06 追加]
PhoenixのBIOSは、サスペンド用の領域をディスクに確保するのだが、それが2GBを越える位置に存在すると、起動できなくなってしまうという「お間抜けな仕様」である。
このため、HDDを取り付けて、DOSのFDで起動してから「phdisk」というユーティリティーで領域を確保するのだが、素直にまっさらなディスクにやっても、2GB近くDOSを切ってから
phdiskしても、一番お尻に確保されてしまい、二度とそのディスクをそのマシンで認識する事ができなくなるというやっかいな事が起きる。
#こうなったら、PhoenixぢゃないBIOSのノートなどに突っ込んで、fdiskで解放しちゃえばまた、Phoenixのマシンで初期化することができます。
植草の場合、Librettoがあったので助かりました。
この辺は、いろいろな人のページを検索エンジンで引っかけるとやり方がたくさんあるようだが、植草のやった方法は....
1.大体メインメモリー+20MBぐらいのサイズで「基本DOS領域」を作る。
2.残りを「拡張DOS領域」で作成する。
3.FDで再起動し、(BIOSが「サスペンド領域がない」って文句言うけど無視)「基本DOS領域」を削除する。
4.もう1回FDで再起動し、phdiskする。
5.またFDで再起動し、「拡張DOS領域」を削除する。(この時点でBIOSは文句言わなくなる)
6.またまたFDで再起動し、サスペンド領域以外は「未使用」となっているので、「基本DOS領域」で全部いただき!!(好みでドライブを分けてもいいと思いますがね)
ともかく、DISKのRead/Writeが桁違いに早くなったおかげで、ずいぶんと良くなった。
数字的には、植草のきゃんびぃーの2GBよりも倍以上早くなっている...
★ ★ ★ HDBENCH Ver 2.510 ★ ★ ★ 使用機種 Processor Pentium 99.5MHz [GenuineIntel family 5 model 2 step 5] 解像度 1024x768 256色(8Bit) Display Chips & Technologies 65545 PCI Memory 40,020Kbyte OS Windows 98 4.10 (Build: 1998) Date 1988/11/ 8 18: 1 HDC = CMD PCI-0640 PCI to IDE Controller HDC = プライマリ IDE コントローラ (シングル FIFO) HDC[?]=セカンダリ IDE コントローラ (シングル FIFO) A = GENERIC NEC FLOPPY DISK C = GENERIC IDE DISK TYPE40 Q = TEAC CD-40E Rev 2.0P ALL 浮 整 矩 円 Text Scroll DD Read Write Drive 3368 5741 6064 1481 576 1600 13 2 5638 5837 C:10MB